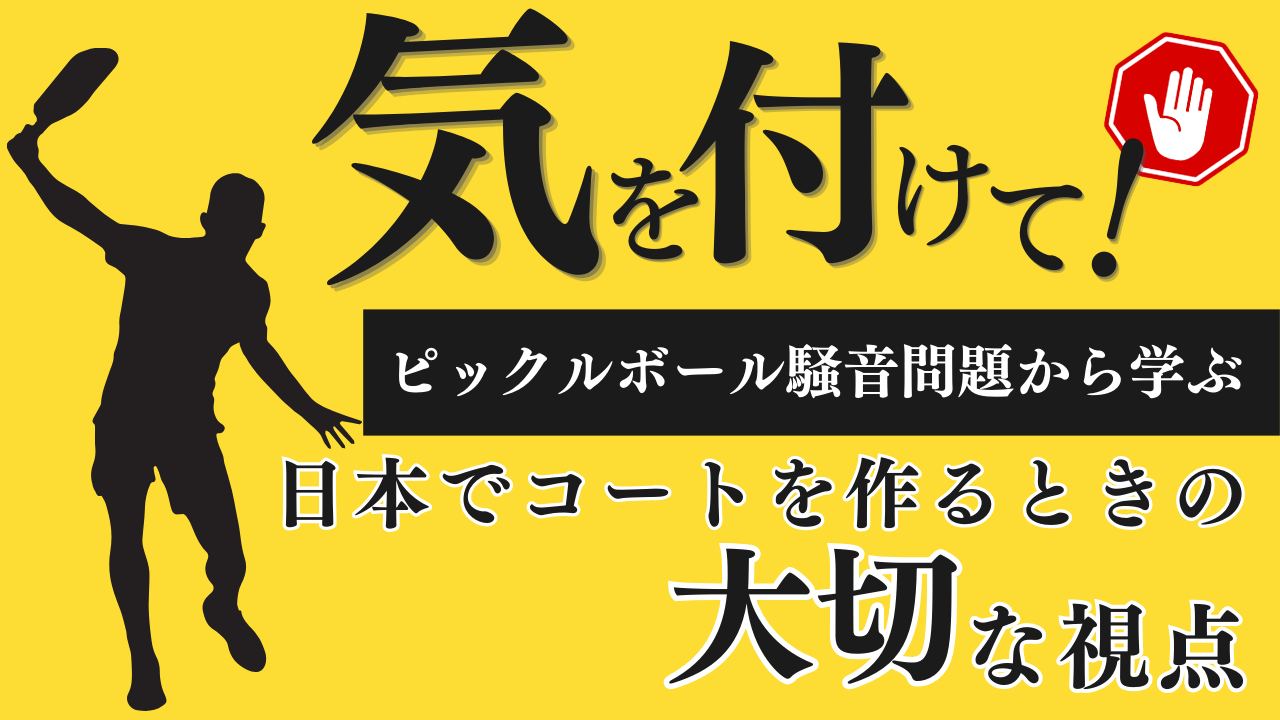「ポンッ、ポンッ」――ピックルボールの軽快な音。
実際にプレーした人なら、この音に親しみを感じるでしょう。ですが、アメリカではこの「音」が社会問題に発展しているのをご存知でしょうか?
ピックルボールは誰でも気軽に楽しめる反面、パドルとボールがぶつかると高めの「カンッ」という衝撃音が響きます。この音が、静かな住宅街や公園周辺で大きな論争を呼んでいるのです。

アメリカで相次ぐ「騒音トラブル」
アメリカの各地では、ピックルボールの音をめぐって住民が市や団体を訴えるケースが相次いでいます。
コロラド州ローンツリー:訴訟に発展
コロラド州ローンツリー市では、6面のピックルボールコートを持つ施設をめぐって、住民5名が地方自治体を相手取り訴訟を起こしました。音量測定では平均62.1dBAとされ、州の基準を超えていたとのことです。
🔗 The Dink Pickleball
フロリダ州ヒルズボロ郡:騒音対策をめぐり調査と規制検討へ
フロリダ州ヒルズボロ郡では、住民による騒音苦情を受けて、郡議会が「住宅から250フィート以内での新規コート設置を一時停止すべき」という提案を検討しました。
しかし、この“一時停止案”は賛成3・反対4で否決。代わりに、「近隣住民の生活の安全を守るため、適切な距離の研究や音量規制の検討を行う」ことが全会一致で可決されました。
🔗 FOX 13 News
サンディエゴなど各地で訴訟
サンディエゴなど一部地域では、ピックルボールの音をめぐって住民が実際に法的措置を取り始めています。
また、フロリダ州ネイプルズのように「ピックルボールの聖地」と呼ばれる街でも、近隣住民からの騒音苦情が絶えず、規制を求める声が高まっています。
アメリカでは、こうした問題が“社会問題”として取り上げられるまでになっています。
🔗 KPBS
ピックルボールの音と、その解決への動き
ピックルボールの打球音は「カンッ!」という鋭い響きが特徴です。しかもラリーが続くたびに同じ音が繰り返されるため、コートの近くに住む人にとってはトラブルの原因になることもあります。
調査によれば、コートから30メートル離れた場所でも平均70デシベルに達し、これは静かな住宅街(約40デシベル)よりずっと大きく、車の通行音に近いレベルだといいます。
🔗 Crazy Pickleball Lady
さらに環境コンサルタントによると、55デシベルを超えると生活に支障が出やすいとされ、住宅から150メートル以上離してようやく「気になるレベルが減る」との分析もあります。
🔗 South Seattle Emerald
こうした背景を受け、USA Pickleball(全米協会)は2023年に「静音カテゴリ」の器具開発に着手しました。これは、従来よりも音量を大幅に抑えられるパドルやボールを認定する仕組みで、メーカーと協力して開発を推進しています。実際、2023年に認定された OWL Sport社のパドルは、通常のパドルと比べて打球音を50%削減することが確認されました。
🔗 USA Pickleball – Quiet Category
さらに一部の自治体では、防音フェンス 「Acoustifence」 や吸音パネルを導入するなど、環境面での対策も進められています。実際に10 dBA以上の騒音を減らせる効果があるとされ、すでに北米の公共施設で利用実績があります。
🔗 USA Pickleball – Acoustifence

日本でコートを作るならどうする?
ここで考えたいのは、「もし日本でピックルボールコートを作るなら?」ということ。
まだ国内では大規模な騒音トラブルは報告されていませんが、人口密集地が多い日本だからこそ、あらかじめ配慮が必要です。
配慮ポイントまとめ
- 住宅地から距離をとる:アメリカでは150m以上離すのが目安とされています。
- 防音設備を設置:吸音フェンスやシートを設けて音漏れを抑える。
- 時間制限を設ける:早朝や夜間は利用禁止にして近隣への負担を減らす。
- 地域と話し合う:説明会や体験会を開き、「どのくらいの音なのか」を共有する。
こうした対策を講じることで、地域と共存できるコートづくりが可能になります。
まとめ —— 「音の問題」は未来のヒント
アメリカの騒音問題は「人気の裏返し」でもあります。
それだけ多くの人が楽しんでいるからこそ、地域との摩擦が表面化しているのです。
日本でピックルボールが広がる前に、この事例を知っておくことは大切です。
「どうすれば誰もが安心して楽しめる環境を作れるか?」――それを考えることが、ピックルボールを文化として根づかせる第一歩になるのではないでしょうか。